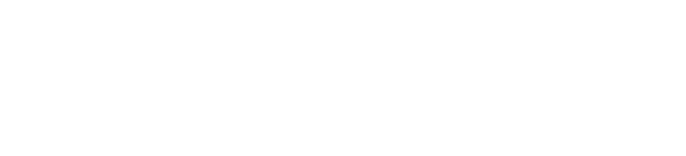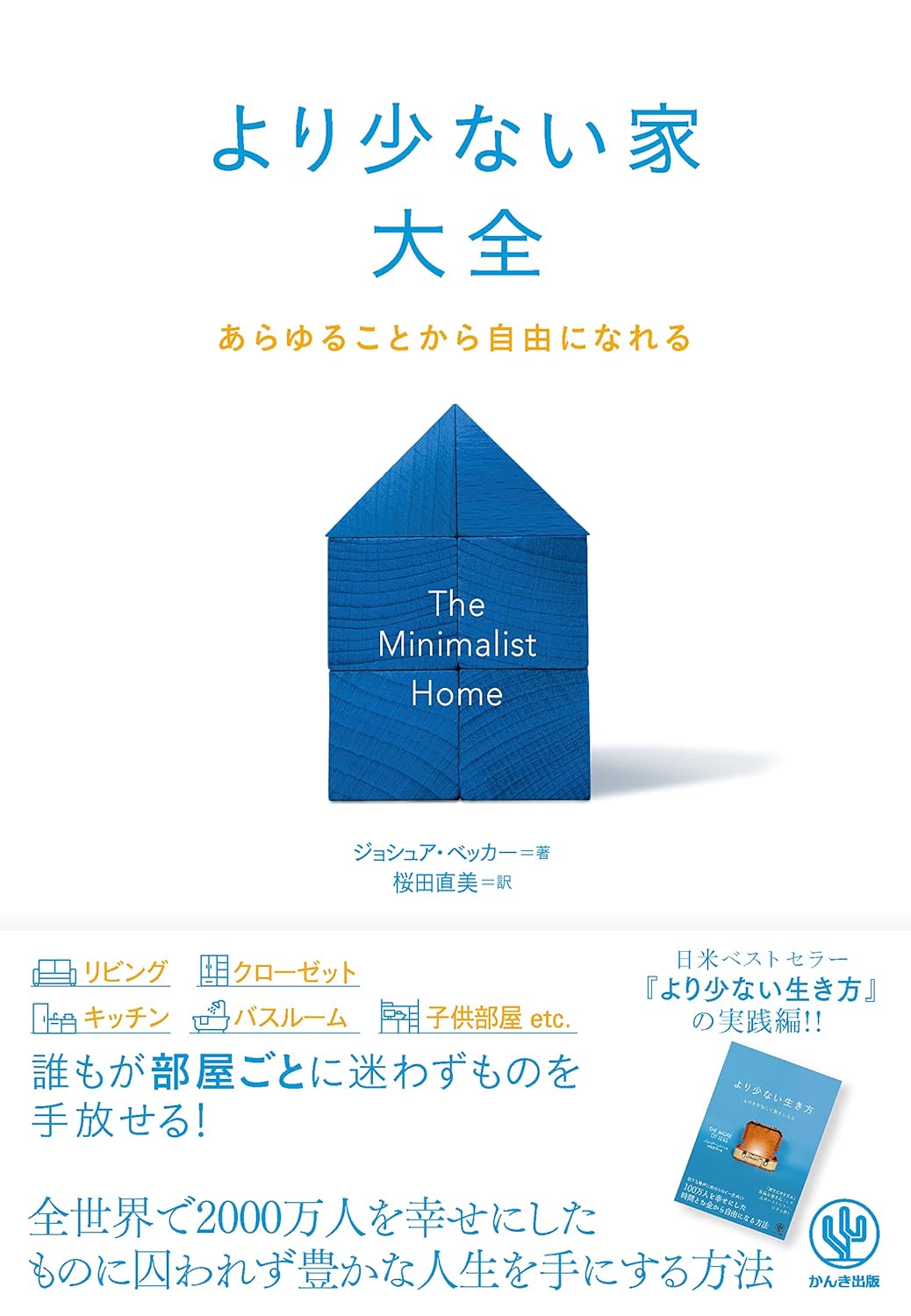私は自称ズボラ系ミニマリストで、すでに多くのものを手放し、少ないもので暮らしています。
もともと収集癖のあるオタクだったこともあり、これまでにかなりの量のものを処分してきました。
それでも「これで完璧」とは思っていません。ミニマリズムは終わりのないプロセスであり、持ち物や暮らしの見直しは定期的に行う必要があると感じています。
最近、ジョシュア・ベッカー氏の『より少ない家大全』を読みました。
これからものを減らそうとしている人はもちろん、すでに身軽な生活を送っている人にとっても、暮らしをさらに整えるためのヒントが詰まった一冊です。ここでは特に印象に残った部分を紹介します。
「おうち」は地球上でもっとも大切な場所ということ
この本の第1章のはじめに「おうち」は地球上でもっとも大切な場所と書かれています。
自宅に満足できないのは、ものが足りないからでも、整理整頓が苦手だからでもなく、広告や店から押し付けられた“理想の家”にとらわれているからではないか──著者のジョシュア・ベッカー氏はそう問いかけています。
自分が本当に心地よく過ごせる家とはどんな場所なのか。
自分軸で考え、持ち物を見直していくことの重要性が丁寧に書かれていると感じました。
また、家を好きになれなくなる原因の多くは、ものを増やしすぎたことにあるとも書かれています。
よほど整理整頓が得意で几帳面な性格でもない限り、たくさんのものを管理し続けるのは困難です。
私自身、若い頃は本や雑誌、テレビで見た「理想の暮らし」を真似した時期もありましたが、多くのものをきちんと管理するのは無理だと気づき諦めました。
ある程度ものがあっても整って見せるには相当なセンスが要りますが、「片付いた部屋」を作るだけなら、ものを減らすことで比較的簡単に実現できます。
ミニマリスト=何もない白部屋のイメージは世界共通?
本書では、ミニマリズムという言葉の解釈を多くの人が誤解していることについても触れられています。
『白い箱のような殺風景な家で、中はほぼ空っぽ』という表現を見て、国が変わってもミニマリズムには共通したイメージが存在するのだなと感じました。
著者の提唱するミニマリズムとは、とにかく所有物を少なくすることです。
自己表現のためのアートではなく、物を持たないことが偉いという価値観でもない。
ミニマリズムは、極端に禁欲的な人だけのものではなく、みんなのものであると書かれています。
アートのように洗練されたミニマルな部屋も素敵ですし、真っ白いインテリアも個人的にはめちゃくちゃ大好きです。なのでそのような部屋を批判する意図はないです。
ただ、「それこそがミニマリストである」というイメージを持った結果、「自分には無理だ」と思ってしまう人がいたら、それはもったいないことだと思います。なぜなら、ミニマリズムとは暮らしを整えるためのメソッドであり、何もないがらーんとした部屋を目指すためのものではないからです。
適正なものの量は人それぞれです。
自分にとって必要なものなら、実用性がなくても好きな雑貨を飾っても良いんです。「〇〇を持っているからミニマリストではない」と他人にジャッジされるものでもありません。たとえ他人から見ればガラクタでも、自分が見て癒され、心地よく感じるものであれば、無理に手放す必要はないと思います。
ものを減らして豊かになる『ベッカー・メソッド 』について
自宅をミニマル化する際に、効率的でリバウンドしにくい方法として、著者が提唱する『ベッカー・メソッド』が紹介されています。以下に要点をまとめます。
- ミニマリズムを始める前に、自宅や人生の目標を決める
- 家族と住んでいる場合、ミニマリズムを家族全体のプロジェクトにする
- 体系的に進める:
・簡単な場所から始め、徐々に難しい場所へ
・ものをひとつずつ確認し、必要かどうか自問する
・使わないものは、売る、寄付、捨てる、リサイクルのいずれかで処分する
・ひとつの場所が完全に終わってから次に進む - プロセスを楽しみ、減らすことのメリットに気づき、成果が上がるたびにお祝いする
- 家全体のミニマル化が終わったら、当初の目標を見直して新たな目標を設定する
この順序で進めれば、効率よく持ち物を減らせそうだと感じました。
また、目標を見直すステップがあることで、リバウンドも起きにくくなると思います。
メソッドごとの具体的な手順がしっかりと書かれており、各項目の最後には『ミニマル化のチェックリスト』がついています。そのため、進捗状況を確認しながら進めることができます。
『簡単な場所から難しい場所へ』の具体的な順番は、本に書かれています。
- リビング
- 寝室
- クローゼット
- トイレ、浴室
- 洗面所
- キッチンとダイニング
- ホームオフィス
- 収納スペース
- ガレージと庭
著者はアメリカ在住のため、日本の住宅事情にそのまま当てはめるのは難しい部分もあります。
それでも、片付けの方法のひとつとして参考になる内容だと思います。
残すもの、捨てるもの
■残すもの
- 目標達成の助けになるもの
- それがあることで良い効果があるもの
■捨てるもの
- 目標達成の妨げになるもの
- 持っていて負担になる、気が重くなるもの
残すものは必ずしも「実用的」である必要はないとジョシュア・ベッカー氏は書いています。
特に印象に残ったのは、「人生の目標がわからなければ、本当に持つべきものもわからない」という言葉です。目標がなければ、ただ部屋を見渡して目についたものを少し捨てるだけで終わってしまうかもしれません。自分の理想や目標がはっきりしていれば、それに沿って持ち物や暮らしを見直すことができます。だから最初に目標を決めることが大切なのだと気付かせされます。
家に残して良いもののは、使用目的がはっきりしていて、その使用目的が人生の目的と合致するものだけ。
この指標に沿って片付けを行うことで、「使っていないけど、もったいないから残しておこう」をなくせます。
不要なものは、捨てる、売る、譲るなどして家から出す必要があります。
人は自分の持ち物の価値を実際より高く感じてしまう傾向があります。
これを『保有効果』と呼びます。
手放すことに心理的損失を感じやすく、客観的な判断が難しくなるのです。
この心理を理解しても、すぐに手放せるわけではありません。しかし、自分が手放しにくい心理状態にあることを認識できれば、客観的に自分を見つめられます。目標に沿わない自分を責めるだけでは、片付けはつらいものになってしまいます。今の自分の状態を認めてあげたうえで手放すことが、リバウンドを防止する意味でも大切だと感じます。
本書には『ミニマリズムが過去を癒す』という言葉も書かれています。
この言葉が救いに感じる人もいるのではないでしょうか。
誰でも取り入れられる、暮らしを整えるミニマリズム
本書では、ミニマリストのフランシーヌ・ジェイ氏の発言として、次の言葉が紹介されていました。
ミニマリズムは「幻想の自分」を自覚し、それと決別するきっかけになる。
幻想の自分とは、自分には合わないものや、本当は欲しくないものを買うことで作り上げた偽のアイデンティティ。
私たちは日常の中で数えきれないほどの広告に触れています。テレビや雑誌、ネット、電車の中吊り広告、街中の看板やポスティングされるチラシなど、そういった広告に触れて「欲しい」と錯覚して買ってしまうことは少なくありません。
本当に欲しいものであるならば、広告を見て買うのは問題ないです。広告をに触れることによって、欲しくもないものを、欲しいような気がして買ってしまうことは無駄な買い物だと感じます。
ミニマリズムの考えを取り入れて家を片付けると、自分にとって本当に必要なものが見えてきます。暮らしを繰り返し整えていくことで、少しずつ自分らしい生活ができるようになり、無駄な買い物もしにくくなります。
ジョシュア・ベッカー氏は、無駄なものを買わなくなった結果お金が残るようになることを「ミニマリズムの配当」と呼んでいます。物理的なものを減らすだけでなく、無駄を減らすことによって、より豊かな生活が実現できるという考えです。
本書は、ミニマリズムは「極端な生き方」ではなく、誰でもはじめられる暮らしを整える手法だと教えてくれる本だと感じました。
自分にとって本当に必要なものを見極め、少しずつ暮らしを整えていくきっかけをくれる一冊です。