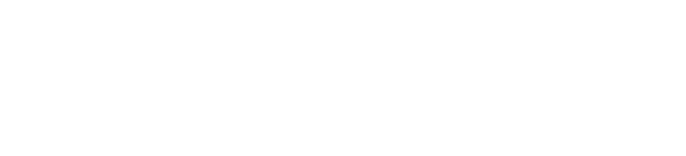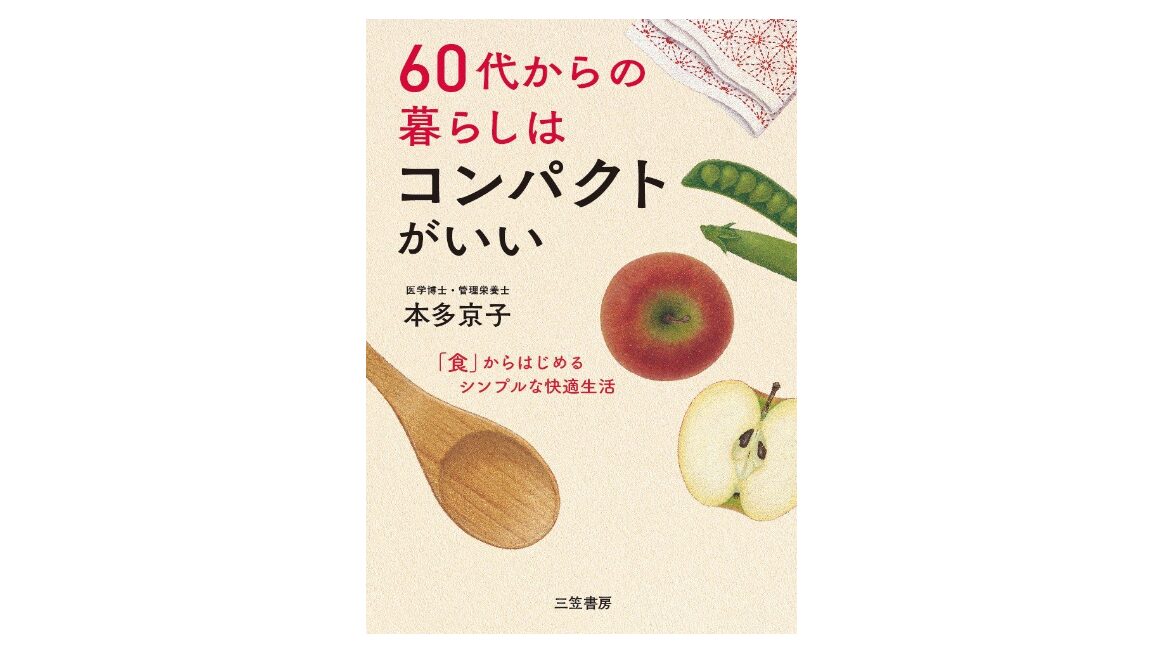本多京子さんの『60代からの暮らしはコンパクトがいい』という本を読みました。
本の表紙に書かれていた『「食」からはじめるシンプルな快適生活』という言葉にひかれて手に取りました。
暮らしを見直すとき、たいていの場合は「持ち物の見直し」から始めることが多いと思います。
しかしこの本では、管理栄養士の著者が一番大切にしている「食」をテーマに、暮らしをシンプルに整えていくという内容になっており、その視点がとても新鮮に感じました。
タイトルに「60代からの~」とありますが、内容は世代を問わず参考になります。
以下、特に印象に残った点をまとめます。
「食」を楽しむことは、人生を楽しむこと
著者は、食べ物に旬があるように、人生にもそのときでしか味わえない「おいしさ=楽しさ・幸せ」があると書いています。「昔はよかった」と過去を振り返ってばかりいると、不幸になる気がする──そんな一文も印象に残りました。
また、食を大切にする人は、自分なりに人生を楽しみ、前向きに生きている人が多いとも述べられています。
確かに、私も「食」を大切にしている人には、人生を楽しんでいる人が多いなという印象を持っています。
食事の回数は人それぞれですが、毎日何らかの形で向き合う「食」を大切にして生きることは、すなわち自分を大切にすることだと感じました。
私も食べることが好きなので、おいしいものを食べているときは本当に幸せな気持ちになります。
おいしく、楽しく、そういう時間を増やしていきたいなと思いました。
食材を無駄にしない工夫
食材を無駄にしないための工夫も、とても参考になりました。
中でも印象に残った点を挙げます。
賞味期限の年ごとにまとめて保管する
この本では、食品の種類ではなく、「賞味期限の年ごと」に分けてストックする方法が紹介されています。
食品をストックする場合は、食品ごとにまとめて保管していることが多いと思います。
例えば、ツナ缶はツナ缶同士で、パックごはんはパックごはんでまとめて保管するような方法です。
この方法では、賞味期限を確認しながら古いものから使う必要があるため、少し手間がかかります。
一方、賞味期限の年ごとに棚やかごを分けて保管した場合は、古い年のものから使うだけなので管理が簡単になります。
私は一人暮らしでストックしている食品が少なく、賞味期限を切らすことがあまりないのですが(切れても気にせず食べてしまう)、ストックが多い場合はこの方法はとても良いと思います。
ショウガは「ウォッカ漬け」で1年も常温保存可能
ショウガの保存方法というと、すりおろしたり冷凍したりが一般的ですが、この本ではウォッカ漬けにする方法が紹介されていました。なんと、常温で1年もフレッシュなまま保存できるそうです。
■ショウガのウォッカ漬けの作り方
- ショウガはきれいに洗って拭き、傷んだところがあれば取り除く
- 清潔な保存瓶に入れ、ショウガが完全に浸る量のウォッカを入れる
- 使う時は必要な分を菜箸で取り出す
野菜を長期保存する場合、切ったり干したり「保存のための手間」をかける必要がありますが、このウォッカ漬けは手間がとても少ない点が素晴らしいです。まとめて漬けておけば、暫くショウガを買わずに済みそうです。
なお、漬け込んだウォッカは料理に使ったり、ドリンクとして飲むことも可能です。
私は普段お酒は飲まないのですが、ショウガの香りのするウォッカはおいしそうでそそられます。
本書には、市販のものを使って簡単に作れるレシピなども載っており、こちらも参考になります。
市販の里芋の煮物と煮豆を使ったおはぎは、一度作ってみたいと思いました。
失われつつある身近にあった「食育」
著者が子どもの頃は、商店街で買い物をしながら食材に関する知識を身に着けていったそうです。
八百屋のおじさんに「どうして曲がったきゅうりのほうが安いのか」と聞き、
「肉じゃがを作るときはどのお肉を買ったらいいか」をお肉屋さんに尋ね、
魚屋さんが魚をさばく様子を見ながら、種類やさばき方を教わったといいます。
商店街のおじさんやおばさんが「食育の先生」だった、というくだりがとても印象的でした。
「食育」とは、教科書で学ぶものではなく、日常の中に自然と存在していたものだったことを思い出させてくれます。
今はスーパーでもセルフレジが増え、誰とも話さずに買い物を済ませられるようになりました。
わからないことがあっても、インターネットで検索すればたいていの情報は出てきます。
ただ、最近はAIによるまとめ情報が上位に表示されることが増えました。
便利な一方、間違った情報も少なくありません。
やはり、食材を扱うプロから直接教えてもらえる情報には、本やネット以上の重みと説得力があると思いました。
食をしっかり味わう、「うまい!」のその先へ
味覚教育の第一人者 ピュイゼ先生からの、最も心に残った言葉として、次の言葉が紹介されています。
「おいしく味わい、味わったことを言葉にする訓練が、人を豊かにする」
「きちんと味わうことをしないと語彙力が衰える」
この言葉には深く共感します。
食事中にスマホを見るのは、もはや珍しいことではなくなりました。何も見ずに食事そのものに集中している人のほうが少ないように思います。私もついスマホを見たり、イヤホンで動画や音楽を聴きながら食事をしてしまいます。
スマホを見ていてもおいしさは感じられますが、どんなふうにおいしかったかを言葉にできるほど、しっかり味わえているかというと、私の場合はそうではありません。
鬼滅の刃の煉獄さんのように「うまい!うまい!」しか出てこない私は、確かに語彙力が衰えているのかもしれません。(煉獄さんの「うまい!」は、きちんと味わったうえでの心からの言葉だと思いますが。)
ただ、言葉にするといっても、普段は使わないような難しい表現で味を語る必要はないと思います。
言葉にするためにはしっかりと味わう必要があり、この「味わう」という行為に大切な意味があるのだと感じます。
私も「うまい!うまい!」で終わるのではなく、しっかり味わいながら食事を楽しみたいと思います。
未来を見据えて、暮らしを軽くする
「最良の選択」をするためには、段取りよく早め早めに手を打っておくことが大切だと、本書には書かれています。年老いた時の体力を考え、予防のために暮らしをコンパクトにしたそうです。
残される人のことを考えて墓じまいをしたというエピソードも印象的でした。以下に引用します。
人間、死んでしまえばリン、炭素、窒素などの元素になって、地中に存在するだけ。
では、なんでお墓が必要なのか、考えました。
お墓はお参りに来る人のためにあります。お墓参りに行くと、気持ちがすっきりしたり、清々しい気持ちになったり、自分がいいことをしたような気持ちになったりする。そのためにお墓があるんじゃないかな、と思ったのです。
それならば、やはり自分のことより、未来を生きる人のことを考えてお墓をどうするか決めるべきではないでしょうか。
この考え方に、深く共感しました。
暮らしを整えることは、最終的には「自分がいなくなったあとの未来を生きる誰かへの配慮」なのだと思います。
高齢になってから持ち物を整理するのは、体力的にも精神的にも大変です。
人は誰しも「今日が一番若い日」です。
今日からでも少しずつ手を打っておくことは、自分にとっても、いずれ片づけを担う誰かにとっても、大きな安心につながります。
この本から学んだことは、生きるために欠かせない「食」を中心に暮らしを整えることが、自分だけでなく、最終的には他の誰かの未来にも良い影響を与えるということでした。
食を通して、日々を大切に生きようと思わせてくれる1冊です。